
日本文化を探る
~日本のサクラ~
3月も中旬を過ぎると、毎日伝えられるサクラの開花状況を聞きながら「来週末には満開かな」とワクワクとした気持ちになります。今年(2021)は、2月から3月にかけての気温が高かったこともあり、観測史上最も早く開花を迎える所が多かったようですね。
気象庁によると、開花の基準となる標本木は、全国に58本。東京は靖国神社、大阪は大阪城公園、京都は二条城にあり、北海道や沖縄などの広いところや離れ島があるところでは、数本あるそうです。樹種としては原則「ソメイヨシノ」ですが、北海道は低温で「ソメイヨシノ」が根付かないため「エゾヤマザクラ」、反対に沖縄は暖かいので「カンヒザクラ」が標本木になっているそうです。
気象庁によると、開花の基準となる標本木は、全国に58本。東京は靖国神社、大阪は大阪城公園、京都は二条城にあり、北海道や沖縄などの広いところや離れ島があるところでは、数本あるそうです。樹種としては原則「ソメイヨシノ」ですが、北海道は低温で「ソメイヨシノ」が根付かないため「エゾヤマザクラ」、反対に沖縄は暖かいので「カンヒザクラ」が標本木になっているそうです。

日本人はいつからサクラ好きに?


ソメイヨシノの中にもいろんなサクラが存在!
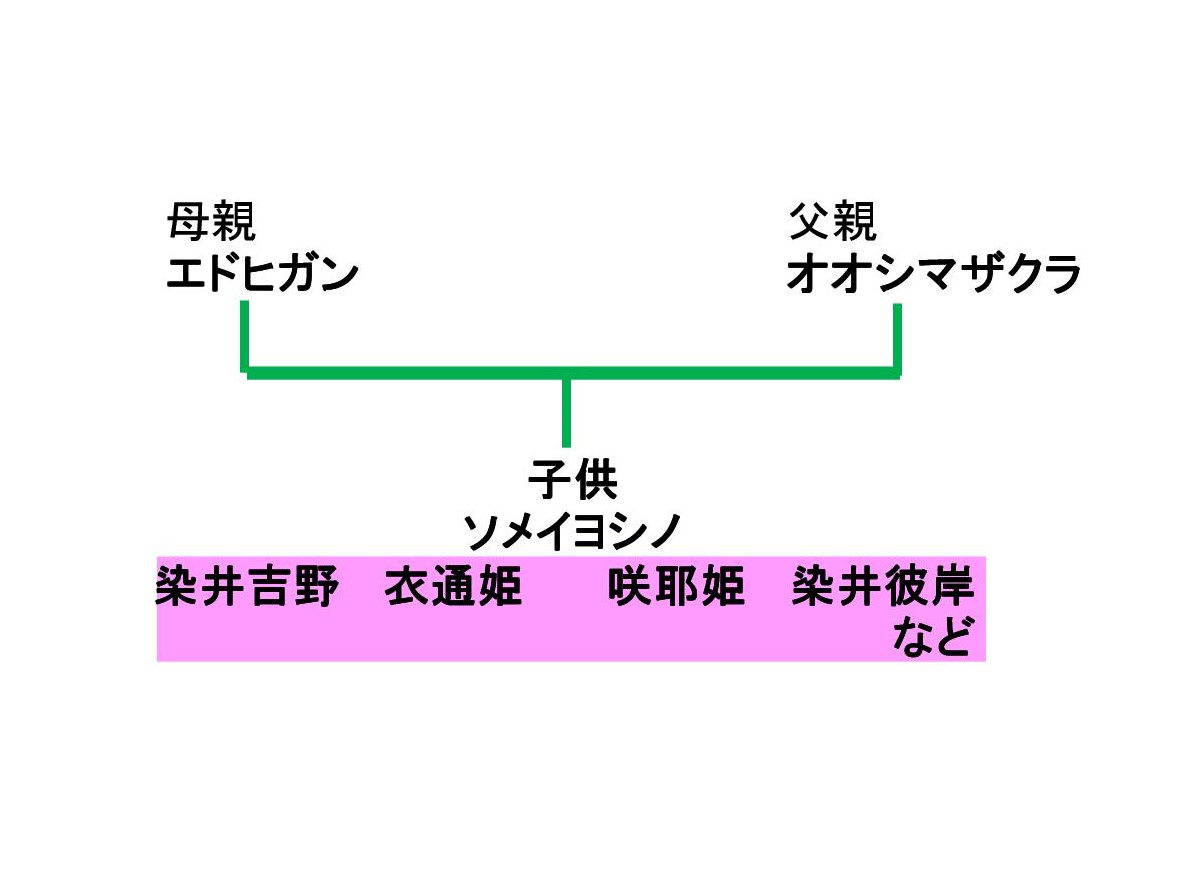
母親がエドヒガン、父親がオオシマザクラ、その子供の総称がカタカナの「ソメイヨシノ」。私たちも同じ親から生まれても、姿形・性格が異なるように、種間雑種の「ソメイヨシノ」にも花びらの色や大きさが異なる子供が生まれるようで、漢字の「染井吉野」や「衣通姫(そとおりひめ)」「咲耶姫(さくやひめ)」「染井彼岸」「染井匂」などのたくさんの子供たちが存在するそうです。「ソメイヨシノ」の中にこんなに品種があるなんて驚きですが、変種や園芸品種を合わせるとなんとサクラの品種は300種以上あるんだそうです。
サクラで有名な吉野のサクラはソメイヨシノ?

「花見といえばサクラ」と世に知らしめ(?)、盛大に行われた豊臣秀吉の「吉野の花見」も「醍醐の花見」もヤマザクラだったということですね。
見るだけじゃないサクラ

どちらにも使われているのが、サクラの葉の塩漬け。塩漬けに使われるサクラの葉っぱは、八重桜。ちなみにソメイヨシノ葉っぱはおいしくないそうです。エリアにより「道明寺」なのか「長命寺」なのかということになりそうですが、それよりも餅を巻いているサクラの塩漬けを食べるか、食べないかが気になります。ちなみに筆者は、口の中がモソモソというか、葉っぱが口の中で残るので、いただかない派ですが、みなさんはいかがでしょうか?
ひと言で「サクラ」と言っても、野生種や変種、園芸品種を合わせると300以上。「ソメイヨシノ」と「ヤマザクラ」は見極められそうですが、そのほかは見極めるのが難しいそうですね。しかし、これだけの数の品種があること自体、日本人のサクラ好きを物語っているような気がします。来年は、従来どおりのお花見ができるといいですね。
ライター:惣元美由紀
画像素材:PIXTA
画像素材:PIXTA
あわせて読みたい
-

「六郷満山」とは
-

身近な日本文化を学ぶ ~正座~
-

身近な日本文化を学ぶ ~天気予測することとは~
-

身近な日本文化を学ぶ 山菜~山の恵みを食すということ~
-

身近な日本文化を学ぶ 仏教における色の意味 ~今も残る色の意味を探る~
-

身近な日本文化を学ぶ ~桝~
-

身近な日本文化を学ぶ ~数珠~
-

冬の花を守るための知恵~冬牡丹・わらぼっち~
-

再興された北野御霊会
-

歳時記シリーズ 6月編
-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の五
-

何げない日常に潜む日本文化~わび・さび~
-

歳時記シリーズ 5月編
-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の四
-

何げない日常に潜む日本文化~日本酒~
-

歳時記シリーズ 3月編
-

何げない日常に潜む日本文化~扇子~
-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の三
-

何げない日常に潜む日本文化~迷信~
-

何げない日常に潜む日本文化~お寿司~
-

歳時記シリーズ 1月編
-
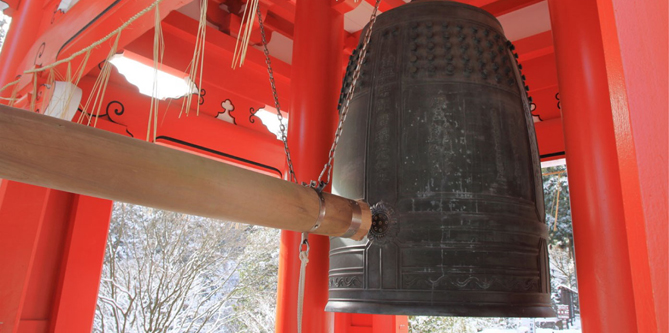
何げない日常に潜む日本文化 ~除夜の鐘編~
-

歳時記シリーズ 12月編
-

何げない日常に潜む日本文化 ~婉曲な表現を好む日本人~
-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の二
-

何げない日常に潜む日本の文化 ~ほうき編~
-

歳時記シリーズ 11月編 ~七五三詣~
-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の一
-

何げない日常に潜む日本の文化 ~お辞儀編~
-

何げない日常に潜む日本の文化 ~「いただきます」「ごちそうさま」編~
-

京都・秋の列車旅。車窓いっぱいに広がる「もみじのトンネル」へ
-

愛される「京野菜」その美味しさを育んだ歴史をひもとく
-

高張とは
-

駕輿丁とは