
日本文化を探る
~桝~
日本伝統の計量器「枡」について

「枡」の歴史

度(長さ)・量(体積)・衡(質量)は中国・朝鮮から日本に伝わり、701年(大宝元年)の大宝律令において「尺・升・斗」などが制定され、これが日本の度量衡制度の始まりと言われています。奈良時代の前なので、飛鳥時代から枡は存在していたんですね。


現在の枡の容量は秀吉が決めた!

現在の生活では、枡を使用する機会がほぼなくなっていますが、枡の単位として「一合炊き」や「一升瓶」という言葉は今も私たちの生活の中に息づいています。また、酒器として、神社仏閣で行われる節分行事など神聖な行事、結婚式などの祝いの席でも使われています。古くは飛鳥時代から使われてきたであろう、日本の伝統の道具「枡」。さすがに容量を計ることは生活の中でなさそうですが、枡に清い酒を注ぎ、その歴史を感じながら飲むのも一興かなと思う次第です。
ライター:惣元美由紀
画像素材:PIXTA
画像素材:PIXTA
あわせて読みたい
-

「六郷満山」とは
-

身近な日本文化を学ぶ ~正座~
-

身近な日本文化を学ぶ ~天気予測することとは~
-

身近な日本文化を学ぶ 山菜~山の恵みを食すということ~
-

身近な日本文化を学ぶ ~日本のサクラ~
-

身近な日本文化を学ぶ 仏教における色の意味 ~今も残る色の意味を探る~
-

身近な日本文化を学ぶ ~数珠~
-

冬の花を守るための知恵~冬牡丹・わらぼっち~
-

再興された北野御霊会
-

歳時記シリーズ 6月編
-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の五
-

何げない日常に潜む日本文化~わび・さび~
-

歳時記シリーズ 5月編
-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の四
-

何げない日常に潜む日本文化~日本酒~
-

歳時記シリーズ 3月編
-

何げない日常に潜む日本文化~扇子~
-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の三
-

何げない日常に潜む日本文化~迷信~
-

何げない日常に潜む日本文化~お寿司~
-

歳時記シリーズ 1月編
-
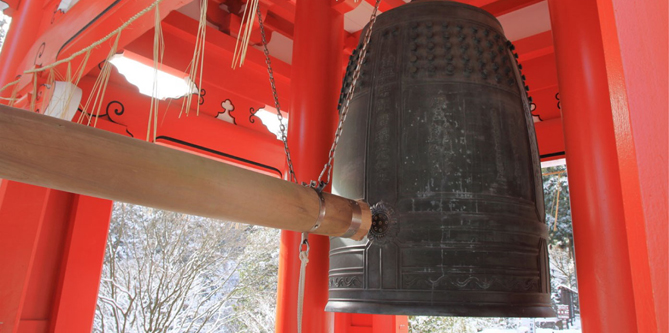
何げない日常に潜む日本文化 ~除夜の鐘編~
-

歳時記シリーズ 12月編
-

何げない日常に潜む日本文化 ~婉曲な表現を好む日本人~
-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の二
-

何げない日常に潜む日本の文化 ~ほうき編~
-

歳時記シリーズ 11月編 ~七五三詣~
-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の一
-

何げない日常に潜む日本の文化 ~お辞儀編~
-

何げない日常に潜む日本の文化 ~「いただきます」「ごちそうさま」編~
-

京都・秋の列車旅。車窓いっぱいに広がる「もみじのトンネル」へ
-

愛される「京野菜」その美味しさを育んだ歴史をひもとく
-

高張とは
-

駕輿丁とは